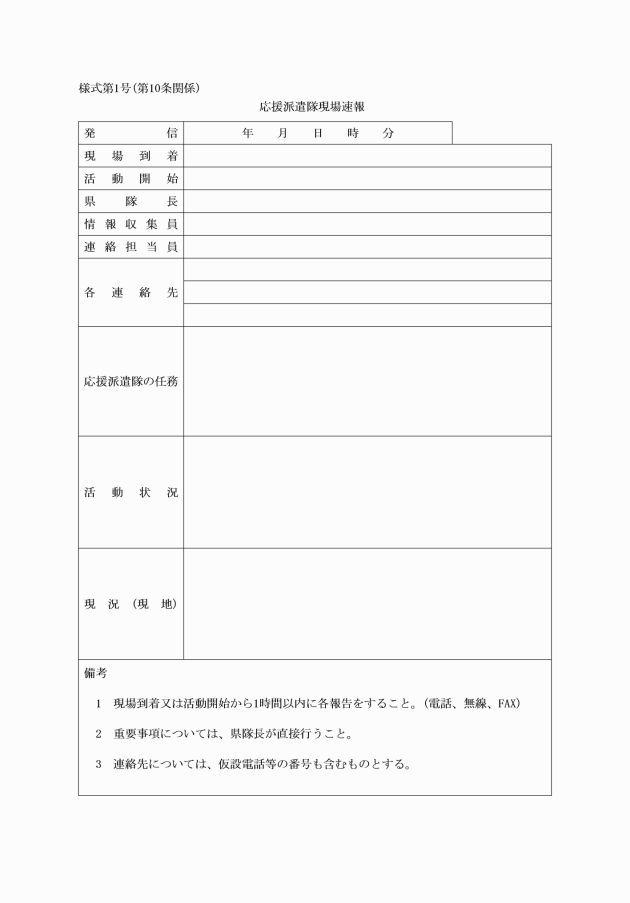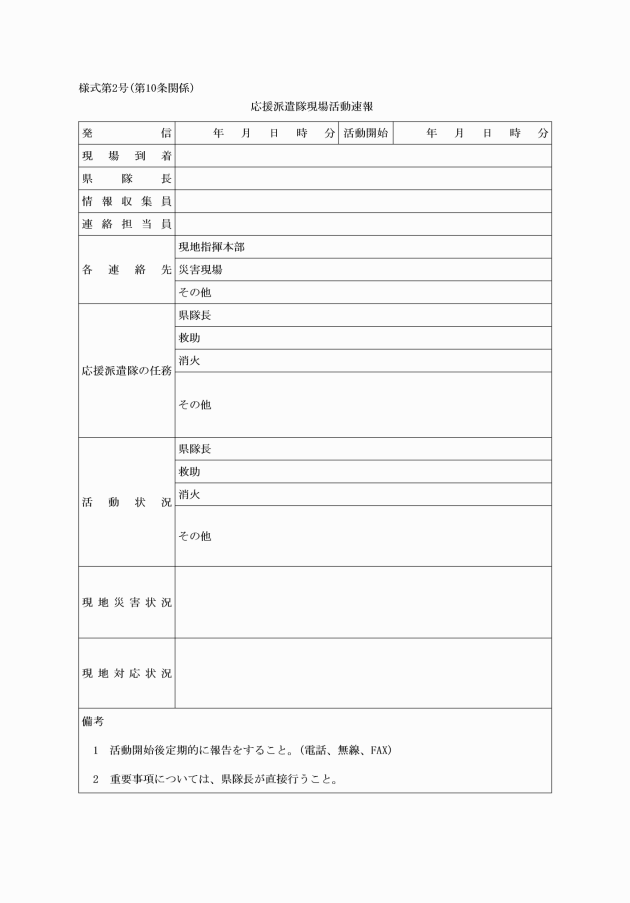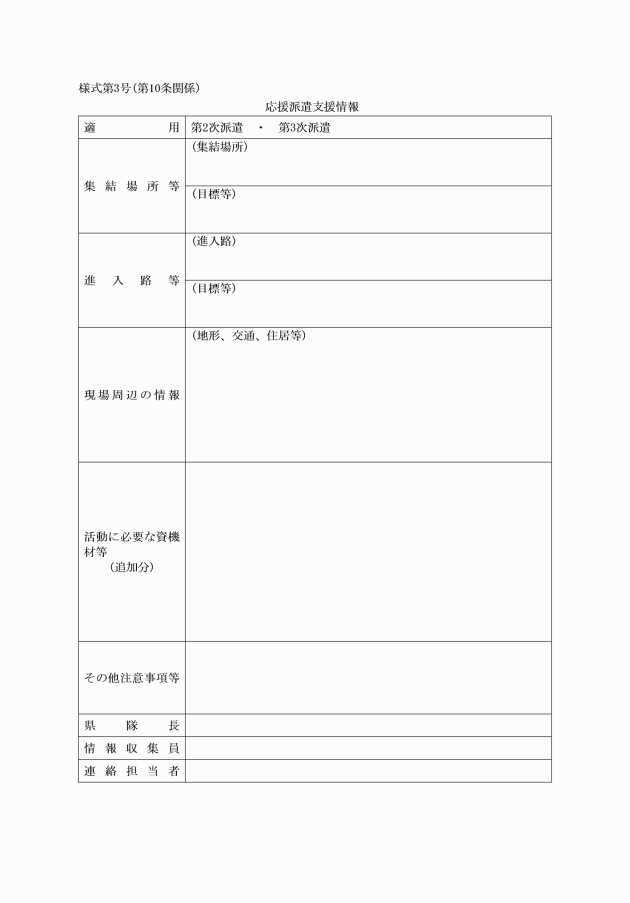○笠間市消防緊急消防援助隊派遣に関する実施要綱
平成18年3月19日
消防本部訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、笠間市消防緊急消防援助隊に関する規程(平成18年笠間市消防本部訓令第23号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(必要装備、資機材等の整備)
第2条 警防課長は、応援派遣時に必要な次の装備、資機材等の計画的な整備に努めるものとする。
(1) 各種災害対応資機材
(2) 野営用資機材
(3) 給食用器具
(4) その他必要と認めるもの
(訓練及び研修)
第3条 消防長は、隊員に高度な技術、知識を習得させるために他の機関の行う合同訓練に参加させ次のことを定期的に実施する。
(1) 合同訓練
消防庁長官、茨城県知事及び代表消防機関の長の実施する合同訓練
(2) 基本訓練及び図上訓練
ア 情報収集、伝達訓練
イ 資機材取扱訓練
ウ 部隊集結、運用訓練
エ その他必要な訓練
(3) 教育
ア 規程及び各緊急消防援助隊に関する消防庁通知
イ 緊急消防援助隊出動事例
ウ その他必要な事項
(隊員の参集及び応援派遣部隊)
第4条 応援派遣出動準備の指示を受けた隊員は、速やかに指定された場所に参集し所属長の指示を受け、次の事項を確認する。
(1) 災害状況の確認
ア 緊急消防援助隊出動指令書(規程様式第3号)
イ 茨城県防災情報システム
ウ その他報道等による情報
(2) 部隊編成及び資機材の確認
ア 出動部隊数及び隊員数
イ 各部隊の隊長及び隊員
ウ 出動車両及び資機材
エ その他必要事項
2 県隊集結
応援派遣部隊は、県隊集結場所に到着したとき、県隊長に到着の報告をし、次の事項の確認を受け災害地の集結場所に向かうものとする。
(1) 報告事項
ア 消防本部名
イ 部隊名
ウ 出動人員
エ 車両、資機材
(2) 確認事項
ア 県隊の構成、車両、資機材
イ 災害地までの進入経路
ウ 無線周波数
エ その他必要事項
(部隊長の責務)
第5条 部隊長は、現場到着したとき、県隊長に部隊名、人員、車両、資機材等の異常の有無を報告し、次の事項を確認した後指示を受ける。
(1) 部隊長は、他の部隊との連携に必要な次の事項を確認する。
ア 災害状況
イ 活動方針
ウ 前進指揮所の位置
エ 使用無線系統
オ 地理、水利状況
カ その他活動に必要な事項
(2) 部隊長は、県隊長の指揮のもと次の事項を任務とする。
ア 応援任務の把握
イ 活動指針
ウ 県隊長との連絡調整
エ 県隊各部隊との連絡調整
オ 隊員の安全管理
(3) 部隊長は、県隊長の引揚げ指示により速やかに活動を終了し、県隊長に次の事項を報告した後、引揚げるものとする。
ア 部隊の活動概要
イ 活動中の異状の有無
ウ 隊員負傷の有無
エ 車両資機材の損傷の有無
オ その他必要な事項
(支援及び調整等)
第6条 支援部隊は、活動部隊の支援活動及び関係機関との連絡調整、野営設営、給食等を行う。
(隊員の責務)
第7条 部隊員は、部隊長の指揮の下一致協力し、応援任務を遂行する。
(応援派遣隊相互の連携)
第8条 応援派遣隊員は、他県隊と協力して応援活動を行うときは、情報の交換、活動支援、資機材の共用等、相互の連携強化に努める。
(携行資機材等)
第9条 部隊が携行する資機材は、部隊装備一覧表(別記1)及び個人装備一覧表(別記2)のとおりとする。
(経費の負担)
第11条 緊急消防援助隊の応援費用の負担については、「緊急消防援助隊の活動に係る経費の負担について」(平成8年4月3日付け消防救第59号消防庁救急救助課長通知)及び「緊急消防援助隊活動費負担金交付要綱」(平成16年4月9日消防震第23号消防庁長官通知)に基づくものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和6年消本訓令第4号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別記1(第9条関係)
部隊装備一覧表
部隊名 | 装備及び資機材 | その他必要な器具等 |
消火部隊 | 緊急消防援助隊の装備の基準 | 衛星電話 |
特殊災害部隊 | 〃 | 衛星電話 |
救助部隊 | 〃 | 衛星電話 |
救急部隊 | 〃 | 衛星電話 |
支援部隊 | 〃 | 寝具、給水、発電機、照明設備、給食用食材、調理用器具、エアーテント、パイプテント、テーブル、その他野営に必要な器具 |
別記2(第9条関係)
(令6消本訓令4・一部改正)
個人装備一覧表
本部 | 個人 | 身の回り品 |
バック(大) | 各部隊用作業衣 | 洗面用具 |
ウエストバック | 編み上げ靴 | 下着類 |
Tシャツ | 略帽 | 筆記用具 |
作業手袋 | 保安帽 | 印鑑 |
タオル | 警笛 | その他必要なもの |
医薬品 | 内服用、外傷用 |
|